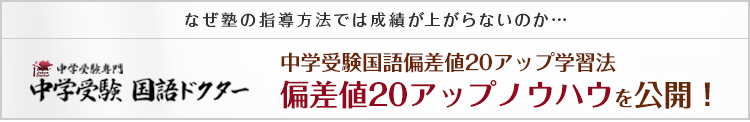こんにちは。
受験Dr.の松本 佳彦です。
中学入試の国語では、様々なことわざや慣用句が登場します。
語彙問題として出題されることもあれば、素材文中に用いられていることもあり、目にする機会は様々です。
そんなことわざ・慣用句のうち、中国の古典を出典とするものを総称して「故事成語」と言います。
「矛盾」や「漁夫の利」が有名ですが、これらの元となったエピソードには「たとえ話」、すなわち実際に起こった出来事ではなく、話者が自分の意見を伝える為に創作した話が多く含まれています。
もちろん、故事成語の意味を理解するには、たとえ話の情景をイメージすることが一番ですが、たとえ話を通して伝えたかった内容を把握しておくと、当時の情勢や思想への興味や理解が深まり、更なる学習へ繋がります。
今回は、有名な故事成語を幾つか挙げ、元になったたとえ話、及びたとえ話を通して話者が伝えたかったことをご紹介したいと思います。
❶「矛盾」
【意味】
2つの物事が食い違っていること。つじつまが合わないこと。
非常に有名な故事成語です。日常会話のみならず、ゲームの題材になったり、2つの物を競い合わせるテレビ番組の名前に使われたり、「実際に同じ強度の素材で矛と盾を作ったらどうなるか?」という議論がなされたり…と、色々な場面で用いられる言葉です。以下に挙げるたとえ話の内容をご存知の方も多くいらっしゃるかと思います。
【たとえ話】
矛と盾を売っていた楚の国の商人。「どんな矛も防ぐ盾」と「どんな盾も貫く矛」を売り文句にしていたが、客の1人から「貴方の矛で貴方の盾を突いたら、どうなるんですか?」と尋ねられ、答えることができなかった。
痛快な物語ですが、あくまでたとえ話であり、実際に起こった出来事ではありません。
では、このたとえ話は何を伝える為に用いられたのでしょうか。
【伝えたかったこと】
中国には「堯」と「舜」という伝説の王様が居た。堯は理想的な善政を敷いた。その後、舜が悪い所を改めて人を助けたのを見て、堯は舜に王位を譲った、とされている。しかし、堯が善政を敷いていたのなら「悪い所」「助けるべき人」が居るはずがなく、舜が人助けをしたというのなら堯の政治に誤りがあったことになる。2人は両立できないではないか。
→徳のある人が政治をする、というのではなく、法律に基づいた政治をすべきだ。
「徳治主義」を批判していた韓非が、自身の説く「法治主義」という考えの正当性を主張しようとして、「矛盾」のたとえ話を用いました。
❷「漁夫の利」
【意味】
2者が争っている間に、第三者が利益を得ること。
「の」を「之」と書いて四字熟語として紹介されることもある故事成語です。
【たとえ話】
シギ(鷸)という鳥がハマグリ(蚌)を食べようとくちばしでついばんだところ、ハマグリが殻を閉じてしまった。お互いに相手を放さないでいるうちに、やって来た漁師に両者とも捕らえられた。
シギ(=鷸、いつ)とハマグリ(=蚌、ぼう)が相争っている為、「鷸蚌(いつぼう)の争い」という言い方がされることもあります。原文では、話の中で「このままだと干からびたハマグリになるぞ」「このままだと飢えたシギになるぞ」というセリフが出てきます。シギやハマグリが人間の言葉を発することはありませんから、これもたとえ話です。
【伝えたかったこと】
趙という国が燕という国を攻めようとしていた。小国である趙と燕が互いに争うのは、シギとハマグリが争うようなものである。
→漁師にあたる大国(秦)に、2国とも攻め込まれてしまう。
燕の蘇代という人物が趙に赴き、王様が燕に攻め込むことを止めさせる為に、「漁夫の利」のたとえ話を用いました。
ちなみに、この「秦」という大国は、「鶏口となるも牛後となるなかれ」等、別の故事成語でもよく登場しています。
❸「五十歩百歩」
【意味】
多少の違いはあっても、本質的には同じであること。
悪い意味で「大差のない」時に使う言葉です。「どんぐりの背比べ」ということわざも似た意味です。
【たとえ話】
激しい戦の最中、戦場から逃げ出した兵士が居た。50歩逃げた兵士が、100歩逃げた兵士のことを笑ったとしたら、それは如何なものだろうか。
原文では、孟子に上のように尋ねられた魏の恵王は、「それはおかしい。どちらも逃げたことに変わりがない」と答えています。では、そもそもこのたとえ話はどういう文脈で出てきたものでしょうか。
【伝えたかったこと】
恵王が孟子に、「私は民のことを考えて政治をしており、他の国の王が私と同じようにしている様子はありません。それなのに、何故魏の人口は増えず、また他の国の人口は減らないのでしょうか。」と尋ねたところ、孟子は上のたとえ話を用い、「王様が『どちらも逃げたことに変わりがない』ことを理解しているのなら、人口が増えることを望んではいけません」と説いた。
→恵王の今の政治は、他の国の政治と大差ない(優れたものではない)。
性善説を主張する孟子が、「民の衣食住を満たし、家族を養えるようにすることが、民が道徳を守る第一歩だ」という、政治の王道を説く為に用いたたとえ話です。
いかがでしたでしょうか。
今回紹介したもの以外にも、「虎の威を借る狐」や「井の中の蛙」のように、たとえ話が元になった故事成語は多くあります。
また、「圧巻」や「漱石枕流」等、たとえ話ではありませんが、実際の面白いエピソードから生まれた故事成語もあります。
故事成語を学習する時には、元となった話の内容もあわせて確認して、理解を深める手助けとしましょう。
今回はこの辺りで失礼いたします。