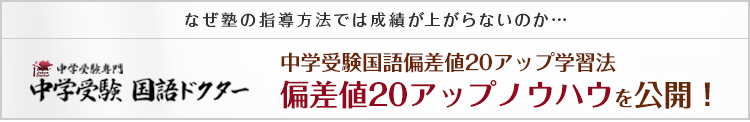こんにちは。
受験Dr.の松本 佳彦です。
本日4月1日は、会社や学校で新年度が始まる日です。
受験Dr.の新年度授業は2月に開始され、生徒の皆さんは既に新学年の授業を受講していますが、本日をもって名実共に「2025年度」の学年に上がる形となります。
――しかし、ここで1つの疑問が浮かびます。「4月1日が新年度の開始であるなら、なぜ4月1日生まれの生徒は早生まれ、すなわち1つ上の学年として扱われるのか?」と。
そこには、教育に関連するいくつかの法律・規則が関わっています。
今回は「早生まれ」をモチーフに、法律の条文を読み解くことで、身近な疑問に対する答えを考えていきます。
❶「年齢計算ニ関スル法律」
最初は、年齢の計算方法を定めた法律です。1902年(明治35年)に施行されたもので、全3項の非常に短い条文となっています。
以下に、今回の早生まれの疑問に関連する条文を引用します。(出典:e-gov法令検索 原文は文語体ですが、分かり易いように口語体に変更しています。)
第1項 年齢は、出生の日よりこれを起算する。
第2項 民法第143条の規定は、年齢の計算にこれを準用する。
※起算…数え始めること 準用…ある規定を他の規定に当てはめて適用すること
第1項により、年齢は生まれたその日を1日目として数え始めます。例えば、「1987年6月10日午後11時59分」に生まれた場合、最初の誕生日が1分で終わってしまいますが、この場合も「1987年6月10日」を生まれた1日目、として考えます。 …㋐
では、第2項に書かれている「民法第143条の規定」とはどういうものでしょうか。年齢の計算にこれを当てはめることになっているようですが…。
❷「民法」
第143条の規定から、必要な部分を引用します。(出典:e-gov法令検索)
第143条第2項 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。(後略)
※応当…~に当たる 満了…一定の期間が終わること
ここでいう「期間」とは、年齢で言うと「0歳の期間」「1歳の期間」…ということになります。先程の「年齢計算ニ関スル法律」により、年齢は生まれた日から数え始めることになっていて、「週、月又は年の初めから期間を起算」するわけではありませんので、民放第143条第2項の規定が適用されます。
先程挙げた、「1987年6月10日」に生まれた人の「5歳の期間」を例にとって考えてみましょう。
「最後の週、月又は年において」→生まれてから5年後、つまり「1992年6月10日」から5歳の期間が始まったので、1年後、つまり「1993年」
「その起算日に応当する日の前日」→「起算日」=「出生の日」=「6月10日」なので、前日は「6月9日」
「満了」→5歳の期間が終了する
また、期間が満了するタイミングは、その日の「午後12時」(=夜中の12時)とされている
これより、この人の「5歳の期間」は「1993年6月9日午後12時」に終わります。「5歳の期間が終わる」とはすなわち「6歳になる」ということですが、この2つは同時、つまり「1993年6月9日午後12時」に起こることとされています。そして、「1993年6月10日午前0時」(=6歳の誕生日)から「6歳の期間」が始まります。 …㋑
これにより、2000年2月29日に生まれた人は、2001年2月28日の夜中12時に「0歳の期間」が終わることになるため、翌2001年3月1日から、問題なく「1歳の期間」に入ります。(4年に1回しか年を取らない、ということはありません)
以上が年齢に関する規則です。「6月9日午後12時」と「6月10日午前0時」は同じ時刻ですが、異なった日付として扱われることがポイントです。
では、学校の年度に関する規則はどのようになっているでしょうか。
❸「学校教育法」および「学校教育法施行規則」
上記2つの規定から、必要な部分を引用します。(出典:e-gov法令検索 「学校教育法」、「学校教育法施行規則」)(数字はアラビア数字に改めてあります)
学校教育法第17条 保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満12歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。(後略)
学校教育法施行規則第59条 小学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
※以後…その時より後 (「以上」「以下」と同様、その日を含む)
「満6歳に達した日の翌日以後」という文言がミソです。
先程の人で言えば、㋑の記述より、「1993年6月9日」が「満6歳に達した日」となります。
その翌日、つまり「1993年6月10日」より後の「最初の学年の初め」は、学校教育法施行規則により、「1994年4月1日」となります。…㋒
よって、この人は1994年の4月から小学校に通うことになります。
ここで、「1988年4月1日」に生まれた人(仮に「ハジメさん」とします)と、「1988年4月2日」に生まれた人(「仮に「ジロウさん」とします」)について、同様に考えます。
●「ハジメさん」の場合
㋐より、「出生の日」は「1988年4月1日」
㋑より、「満6歳に達した日」は「1994年3月31日(午後12時)」
その翌日は「1994年4月1日」なので、㋒より、「満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初め」=「1994年4月1日」
となり、1994年度に小学1年生になります。
●「ジロウさん」の場合
㋐より、「出生の日」は「1988年4月2日」
㋑より、「満6歳に達した日」は「1994年4月1日(午後12時)」
その翌日は「1994年4月2日」(=1994年度の「学年の初め」を過ぎている)なので、㋒より、「満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初め」=「1995年4月1日」
となり、1995年度に小学1年生になります。
これにより、4月1日生まれの人は「早生まれ」となり、4月2日生まれの人と異なる学年に在籍することになります。
いかがでしたでしょうか。
今回は法律や規則の条文を紹介しました。条文は難解な書き方をされているもの、という印象がありますが、文言を1つ1つ読み解いていくと、何を伝えたいか、ということが分かってきます。
中学入試の国語でも、論説文では自然科学や哲学のように難しいテーマが出題され、本文中には専門用語が数多く登場します。一読しただけでは内容を読み取れないかもしれませんが、上のように内容を細かく分析することで、筆者の主張が明らかになっていきます。
また国語に限らず、算数や理科、社会の問題文についても、文意を取りにくいときには、内容を図に起こす、条件部分を抜き出す、などの方法で少しずつ読み進めていくと、全体像が見えて来ます。
書かれている内容を別の表現で言い換えながら、文章の意味を理解する練習を重ねましょう。
今回はこの辺りで失礼いたします。