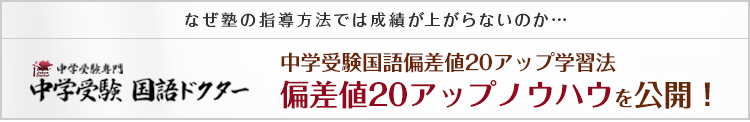こんにちは、受験Dr.の太田 陽光です。
前回、物語文での新年度開始時に知っておいてほしいことを書きましたので、
今回は、論説文でのこの時期に知っておいてほしいことを書きます。
それは、頻出解法パターンの一つ、
キーワードと同じ意味の言葉を見つける、特に線部から遠い所で見つける、というものです。
ここでいう「キーワード」とは、
問いで聞かれている言葉や、
線部にふくまれている言葉、
線の前後にあり問いに関係する言葉(たとえば、線部に指示語があり、その指示語が指し示す、線部の前にある言葉)
などのことです。
論説文では、線部の前後を読んだだけでは答えが見つからない問題があります。
文章全体を見て、どこにどんな内容が書かれていたかという文章構成の理解を問われることがあります。
ですので、実際に新学年になったばかりのこの時期に、
頻出解法パターンの一つを、
そしてそれに付随して、論説文を読むときにすべきことを知っておきましょう。
では実際に、どんな問題が出るのかを、入試問題・塾でのテストや教材から見ていきます。
3段階に分けて説明します。
1 同じ言葉を見つける
玉川学園中学部の2024年第1回の入試問題の大問10で以下の問題が出ました。
(4)-線部3「学問というもの」はどのようなものであると筆者は考えていますか。
この問題では、「学問」をキーワードにして探します。
すると線部の5行後ろに「それが学問というものである。」という表現があったので、
それが指す内容が答えとなりました。
もう一問挙げます。
最後から2番目にきた本文全体の要旨に関する問題です。
(14)「知の体力」について筆者の考えを次のようにまとめました。A~Fに当てはまる言葉をそれぞれ文字数に従って文中からぬき出しなさい。
今回は当然「知の体力」がキーワードです。
「知の体力」というキーワードは、本文が198行ある中の、9行め、146行め、196~197行めの3か所にありました。
この問いには線が引かれてなかったのですが、
最後から2番目の問いであり、
文章の終わりに「知の体力」という言葉があるため、
196~197行め辺りで答えを探してしまう受験生が必ずいると想像できます。
しかし答えはA~Cが146行めの直前直後2行以内に、D~Fが9行の後ろ20行めまでにあるものでした。
「知の体力」というキーワードを文章全体においておさえられていたかが問われた問題だということがわかります。
2 同じ意味の言葉を見つける
日能研の2025年6年学習力育成テスト第13回の応用問題大問7で以下の問題が出ました。
問2(2)「最初の前提は誤り」だと反論している筆者は、「どのような理由から、何をどのように考えたほうがよい」と述べていますか。50字以上60字以内で書きなさい。
問いの「理由」や「考えたほうがよい」をキーワードにすると、
理由→原因
考えたほうがよい→考察されるべき
という表現があり、そこが答えになるとわかります。
また、四谷大塚予習シリーズ6年上9回大問2では以下の問題があります。
問4 -線部①「外国語」というのはひとつの道具みたいなもの」とありますが、「道具みたいなもの」を別の言葉で言い換えた部分を文章中から6字でさがし、ぬき出して答えなさい。
「外国語」をキーワードとして探すと、
「英語」という外国語の具体例に言い換えたものがあり、その近くに答えがあります。
キーワードと一字一句同じ表現でなくても、同じ意味の言葉を見つけることが求められています。
3 本来なら違う意味だが、文章中では同じ意味と解釈すべき言葉を見つける
四谷大塚予習シリーズ6年上7回 イコールの関係②換言の説明に以下のことが書いてあります。
A日本の知識人には論理コムプレックスとも言うべきものがつきまとっている
B日本人は…論理的であることはつねによいことであり…そういう固定観念がいつのまにかできてしまっている。
A「論理コムプレックス」と、Bの「日本人は…固定観念」が同じ意味である。
A文末「~つきまとっている」とB文末「~いつのまにかできてしまっている」との類似にも注目。
「つきまとっている」と「いつのまにかできてしまっている」とは本来違う意味ですが、
この文章では、同じ意味と解釈できるものです。
このつながりに対し納得することができるのであれば、換言力・解釈力が高いと言えます。
では、線部から遠い所でキーワードを見つけるという解法を身につけるにはどうしたらよいのでしょうか。
それには、
自分がこの文章で大切だと思う言葉や文を覚えておくために、
もしくはすぐに探せるように、
目印として言葉や文に線を引いたり、印をつけたりすることがやはり必要になるのです。
本文に印をつける理由が分かりましたか。