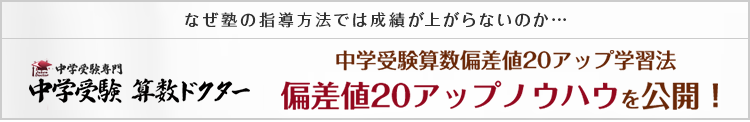みなさん、こんにちは。受験Dr. の坂井です。
新学年になり2か月が経過しました。新学年になったばかりのころは1週間の学習量が増えて大変だったと思いますが、それももう慣れてきたころではないでしょうか。
さて、受験生のみなさんは成績を上げることを目標に日々学習に取り組んでいることでしょう。しかし、学習に取り組んでいても正しい学習方法で学習が行われていなければ効果が上がりにくくなります。今回はみなさんの学習の取り組みの中で「復習」がいかに重要であるかというお話をします。言い換えると「復習」がみなさんの学習のプロセスに存在しなければ成績は上がりにくいというお話です。
同じ学習量でも学習プロセスの違いで成果に差が出る
算数が苦手で・・・、答えを覚えるほど問題演習しているのに・・・、など算数についてお困りの受験生の学習スケジュールを掘り下げていくと、共通していることの1つに「復習」が学習プロセスにないということが挙げられます。
塾で新しい単元を学習した後、家庭学習で課題の数値替え問題を解く。この学習プロセスで学習を完了させている受験生が多いように思われます。その学習プロセスの中で、わからない問題を塾の先生がかいた板書をたどったり、真似したりする「考える」時間をしっかり確保していれば、理解までたどり着きます。この作業が「復習」といえる部分です。そして理解できた状態で課題の類似問題を自力で解くことができるかどうかを確認してこそ学習の効果が生じます。
理解しているかどうかわからない状態で、とりあえず課題を解く。わからない問題は何となく解答解説を頼りに何とか答えまでたどり着く。こういった状態で学習を完了させてしまった場合、再度類似問題を解いても自力で解けないことが多いでしょう。これが誤った学習の始まりで、この後にとる学習行動は無意識に解き方を覚えるという作業になっていきます。まじめにこの作業をたくさん繰り返す受験生は、短期記憶により学習直後のテストでは点数が取れますが、問題をひとひねりされた出題や出題範囲のないテストになると点数が取れないという現象が起きます。
家庭学習で同じ時間をかけて取り組んでいる受験生でも、実力テストのような出題範囲のないテストで大きく差が生じる原因は、塾で習った直後の「復習」をしているかしないかの違いである可能性があります。まじめに取り組んでいるのにテストで成果がなかなか上がらない受験生は、自分の学習プロセスに「復習」の時間が存在しているかどうかを振り返ってみることをお勧めします。
復習するための重要アイテム
塾で習った直後に「復習」するために必要なものは、塾の授業での板書です。授業では考え方を作図や表などを用いて解説してくれます。どんなに集中して授業を聞いていてもすべてを頭の中にいれて持ち帰ることはできません。わからない問題を解決してくれるために必要なものは授業の板書なのです。算数の考え方の土台がしっかり定着している受験生であれば、配布される解説をみて理解までたどり着ける問題もあるでしょうが、解説は簡略化されていることが多く、それを見ただけで理解できないことも多いはずです。算数が得意な上位生でも解説をみても解決できない問題は多いのです。板書をとる際の注意点は、式の部分だけ板書をとってきても意味がないということです。重要なのは考え方を理解するための作図や表なのです。
授業で解説したことを生徒自身で再現できることが重要
受験Dr.では授業で解説した内容を生徒自身で再現できるよう指導することが重要であると考え、授業中に発生した板書やメモはすべて持ち帰って頂いています。それをもとに「復習」を行ってもらうためです。「復習」できるようになる生徒から成績は上がっていきます。
「復習」する時間が取れない、ということはありません
よほどの事情がない限り、「復習」する時間が取れないということはないと思われます。「復習」する時間がないという生徒のご家庭とお話をすると、学習に取り組むタイミングがかなり遅いことが「復習する時間がない」ことの原因であることがわかってきます。そういう場合は、生徒が自ら学習するタイミングを早めるように指導していきます。あの手この手を使って・・・。要はモチベーションが上がるように仕掛けを作っていきます。ちなみに、ご家庭でのお声がけで「がんばったら○○買ってあげる」という類のものはNGです。一歩前進させるどころか一歩後退させてしまいます。
「復習」は直後に行うことが効果的
授業で学習したことを「復習」するタイミングは習った当日、おそくとも翌日です。それ以上時間が空いてしまうと忘却していきます。そして「復習」した際の理解度をテキストの問題番号に〇,△,×などのしるしをつけていくことが重要です。△や×のしるしがついた問題はその後再度確認する必要があるからです。テスト前においても、どの問題を再チェックすればよいかがすぐにわかります。
「復習」していても忘れることはある
「復習」していてもテスト前に再度問題を解いたら解けないということはあります。忘れてしまったのです。しかし、「復習」により一度理解するところまで到達しているので思い出すまでに要する時間は短時間で済みます。そして確認することでさらに定着していきます。もし、解き方を覚えてしまう学習をしていた場合は、はじめから学習し直すことになり、それが時間のないテスト前であれば、焦りを生じさせます。その繰り返しが受験生の自信を失わせる原因になっていくこともあるのです。
正しい学習プロセスのまとめ
1「復習」はタイミングが重要
「復習」をいつ行うかということが最も重要なことです。「すぐ」やることです。①塾から帰ってきて「すぐ」に行う。②テストが終わって帰宅したら「すぐ」行う。この2点につきます。そして、本当に解けるかどうかは、まだこの時点では判明しません。
2 学習したことが本当に理解できているのか(再現性の有無)を確認する
課題で出された類似問題を解く際に、学習したことが自力で解けるかどうかを確認します。学習内容が本当に理解できているかどうかが判明するのはこのときです。。正解までスムーズにたどり着けなかった問題は△、わからなかった問題は✕などの印をテキストの問題番号につけていきます。印のついた問題は、後日再度確認が必要になります。
さあ、これから春期講習が始まります。塾の授業も連日行われ学習量も多くなる期間ですが、ぜひ学習サイクルに「復習」する時間が取れているか、改めて確認してみてください。
応援しています。一緒に頑張っていきましょう!
それでは、またお会いしましょう。