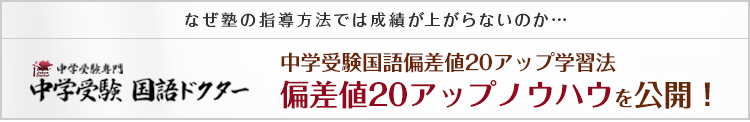こんにちは。
受験Dr.の佐倉です。
2月は中旬に入りました。
暦の上ではすっかり春です。
新学年が始まります。
よく、学年が上がるに伴ってテキストの難易度も上がり、ついていけなくなってしまったというお悩みを耳にすることがあります。
国語でも、特に自然科学や環境問題に関する説明的文章については、何を言っているのかわからないと首をかしげる生徒が多いです。
高学年になると、難解な文章を扱うことが増えます。たとえ本文が難しくても文章の内容を全てしっかりと理解したい/させたいという気持ちは大切ですが、それは現実的ではありません。
しかも、試験は時間が限られています。
短い時間の中で、正確に、その文章が何を伝えようとしているのかを読み取ることが、受験では必要なのです。
では、どうしたら良いのかというと、全てを理解しようとしないようにするのです。
文章の意味がわからない、と言うお子様にも、様々な理由があります。
語彙力が少ない、読み進めるうちに何の話をしていたのかを忘れてしまう、そもそも長い文章は頭に入ってこない、など……
いずれにせよ、大切なのは、本部の重要な部分とそうでない部分を分けて理解することです。
文は、長ければ長いほど、理解するのが難しくなります。
少しでも「何を言いたいのかわからない」と思ったら、一文を短く区切ってください。
読点で分けるのが視覚的にわかりやすくておすすめですが、もちろん文節ごとに分けても大丈夫です。ついでに係り受けの練習もしてしまいましょう。
文は主語と述語で作られます。どれほど長い文でもそれは変わりません。
「誰/何が」「何を」「どうする」の3点を確認しましょう。
他の部分は、上記のことを説明するおまけです。
この3つがわかっていれば、何を伝えようとしているのかが、大まかにでも整理できます。
慣れてきたら、より細かく、5W1Hで分類してみましょう。
5W1Hとは、「いつ」「どこで」「だれが」「何を」「なぜ」「どのように」という情報の要素のことです。
実はこれは、書くときもそうなのです。
言いたいことをどうやって書いたら良いのかわからないと言う話を聞くことがありますが、そんなときは、「誰が」「何を」「どうする」のかたちになるように並べてください。
そこに「いつ」「どこで」「なぜ」「どのように」を加えて説明すると、より詳しい文になります。
主語と述語だけでなく、品詞は覚えて見分けがつくようにしておくと、品詞を直接答える問題だけでなく、文章を読み書きする際にも役立ちます。
2月のうちに文法を学んでしっかりと身に付けておきましょう。
以上、最後までお読みいただき、ありがとうございました。