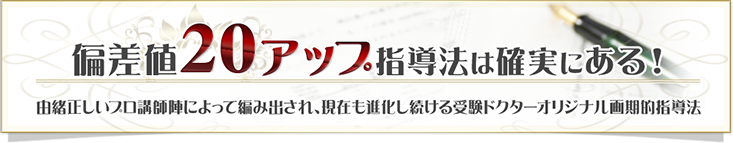皆さんこんにちは!
受験Dr.の清水栄太です。
今回は、盲点になりやすい昭和の歴史に興味を持って学べるヒントについてお話しします。
1926年~1989年まで続いた昭和は、近い過去ですが、苦手とする中学受験生は多いです。
昭和時代はなぜ、苦手になりやすいのでしょうか?
それは、
1 戦争や経済など難しいテーマが多く、身近に感じられない
2 出来事が複雑に絡み合い、全体像を掴みづらい
といった理由が、主な要因として考えられます。
では、ここから昭和時代の歴史の学習のポイントを確認していきましょう!
1 昭和を4つの時代に分けて理解する
昭和は長い時代なので、4つに分けて考えると覚えやすくなります。
前期(1926〜1936年): 世界恐慌と軍部の台頭
戦時中(1937〜1945年): 日中戦争と太平洋戦争
戦後復興期(1946〜1960年代前半): 占領政策と高度経済成長の始まり
安定成長期(1960年代後半〜1989年): 経済大国日本、バブル経済
この4区分を軸に、それぞれの区分の特徴を整理していきましょう。
2 身近な人の思い出とつなげる
昭和時代の学習では、家族(特におじいちゃん・おばあちゃん世代)の体験談を聞くことも効果的です。
ご家族や身近な人の「生きた歴史」を通して学ぶと、これまでの内容がぐっと身近になります。
「おじいちゃん、子どものころはどんな遊びをしていたの?」
「昭和○○年代はどんな暮らしだったの?」
など。
こうした質問をした後で、その答えを歴史年表と照らし合わせてみてください。
「あ、このとき東京オリンピックがあったんだ!」
「この頃は高度経済成長期だったんだ!」と発見があるでしょう。
3 昭和を示す「モノ」から学ぶ
ご家庭にある写真やアルバムなどは、昭和を知る貴重な資料です。
・家族アルバム: 服装や背景から時代を読み取る
・昔のおもちゃ: ブリキのおもちゃ、竹とんぼ、ベーゴマなど
・生活用品: 黒電話、真空管ラジオ、足踏みミシンなど
これらを見ながら、当時の様子を具体的なエピソードを交えて話すと歴史への興味が湧きやすくなるでしょう。
4 昭和の出来事を現代と比較
昭和の歴史を現代と比較することで、変化や連続性を実感できます。
・東京オリンピック: 1964年と2021年を比較
・家電製品の変遷:トランジスタラジオからウォークマン、iPod、スマートフォンへの移り変わり
・食生活: 白米が貴重だった時代から、飽食の時代へ
比較による「差」の発見が、時代の理解を深めます。
5 映像資料の活用
NHKの「映像の世紀」シリーズなどの昭和の記録映像は、当時の雰囲気を感じるのに最適です。YouTubeでも貴重な映像が公開されています。
戦時中の暮らしや戦後の復興風景、東京オリンピック(1964年)、大阪万博(1970年)など、映像による時代のイメージを広げることはとても効果的です。
ここまで5つのポイントをお伝えしてきました。
昭和は決して遠い昔の話ではなく、今の私たちの生活や価値観に直接つながる時代です。
「戦争の悲惨さ、復興の努力、経済成長の光と影、文化の変遷」
これらすべてが、今の日本社会を形作っています。
家族の体験や思い出、品物を通して昭和を学ぶことで、お子さんは「歴史は暗記するもの」ではなく「自分たちの今につながる物語」として理解できるようになります。
身近な人の記憶を借りながら、「昭和」という時代を深めてみてくださいね。
きっとテキストだけでは学べない発見がたくさんあるはずです!
今回はここまで。
それではまた次回お会いしましょう!
応援しています!