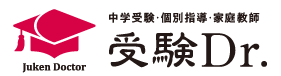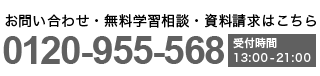太田 陽光先生
分かった時の驚きと感動を大切に

「国語の成績だけがずっと低迷している。」
「国語は、たまにすごく高い偏差値を取ることはあるが、低い偏差値の方が多い。」
「本は好きでよく読んでいるのだが、国語の成績はあまり良くない。」
国語の担当講師として、よく相談を受けることです。
多くの国語の先生が、国語の力を伸ばすいろいろな方法を教えてくれています。
それらは全て間違っていないはずです。
でも、上手くいかないこともある。
私は、いろいろなことをやりすぎているのが問題なのでは、という考えを持っております。
国語で悩みを抱えているお子さまは、
すべきことをしぼる
ことが大切です。
では何にしぼるか?
選択肢の選び方、
抜き出し問題の探し方、
記述問題を書くポイント、
各中学校の出題傾向対策、
もちろんこれらは大切なことですし、必ずすべきことです。
しかし、国語の根幹は「読むこと」です。
国語に対して悩みを抱えているお子さまがすべきこととして、
一つのことだけを意識して読むこと
を私は提案しています。
では、一つのこととは何か?
今回は論説文に関して述べていきます。
「読解力」
ということばをよく目にします。
「読んで解する力」ということでしょう。
しかし、私はこの「読解力」を、
殊に中学受験の国語の論説文においては、
こう解釈しています。
書かれている内容を読んで解する力ではなく、
書かれている内容から筆者の言いたいことを読んで解する力である、と。
以前、「相対性理論」について書かれた文章が出題されました。
皆さんは、その学校が、受験生に対して、文章を読んで相対性理論を解することを求めているとお思いになりますか。
そうは思わないですよね。
恥ずかしながら、私の相対性理論の知識はあやふやなものです。
でも、私はその学校の問題を解けましたし、
そして、その学校に合格したお子様も、解くことができたと想像できます。
なぜか?
その学校が受験生に対して求めたものは、
「相対性理論」について書かれた文章から筆者の言いたいことを読んで解すること
だからです。
私は、文章の内容が全く分からなくても大丈夫だとよく言います。
もちろん、これは極論ですし、
内容が分かっている方が正解を出しやすいのは確かです。
でも、分かる内容のときは、良い点が取れるが、分からなかったら…。
そうです、最初に挙げた、国語の悩みの一つのパターンですね。
内容が難しい文章でも、筆者の意見をとらえる読み方ができれば、大外しはしないと断言できます。
国語の基本ができているお子様とは、安定した成績を取れるお子様だと私は考えています。
そしてこの基本段階の後に、国語をさらに伸ばすために、いろいろな解き方・考え方を身につけることが大切になってくるのです。
国語に悩みを抱えているお子様は
まず、安定した成績を取るために、筆者の意見をとらえる読み方をできるようにすることに集中しましょう。
筆者の意見をとらえる力は、努力で身につけられます。
実は筆者は、「ここを読んでほしい」ということを、ちゃんと教えてくれているのです。
それを知るためには、
筆者の意見のところにある目印のことばに注目すればよいのです。
それを次にあげていきます。
①問いかけ文 「話題」=「これから筆者が言いたいこと」が示された文であるかもしれません。
②逆接 「しかし」「でも」「が、」「のに、」(逆接ではないが似た働きをする「ではなく、」)
前の内容と逆のことが来るときに使う接続語が「逆接」です。論説文では、前の内容に一般的なこと、常識と思われていることが書かれ、逆接の後に、それを否定する筆者の意見が来ます。
例 日本人に「好きな色は何色か?」とアンケートを取ったところ、青が一番多かった。しかし、私は赤が好きだ(意見)。
③「つまり」「こうして」「このように」などのまとめのことば
「つまり」は換言(言い換え)の接続語です。
「こうして」「このように」は指示語です。
言い換えることで、または、指示した内容を短くまとめることで、筆者の意見となっています。
④ポイントを示すことば 「重要」「大切」「大事」必要」「第一」
⑤明らかな筆者の意見を表すことば「私は~」「~思う」「~たい」「~ほしい」
⑥繰り返し使われることば(キーワード)
⑦強調表現「実は~」「~こそ」
⑧強調文末 「~なければならない」「~ではないだろうか」「~べき」「~にすぎない」
普通の「~です」「~だ」で終わればいいところを、わざわざ変えています。
ここには筆者の強い思いが込められています。
⑨例の前後 「例」は筆者の言いたいことを説明するためのものです。となると、筆者の言いたいことは、その前か後ろに、もしくは両方に、あることが分かってもらえるでしょう。
細かく分けたので、9つと意外と多くなってしまいましたが、どうでしょう。
でもほとんどが、中学受験の国語の授業で、きちんと説明されているものです。
問題は、お子さまがこれらを習っていても、自分で読むときにはこれらを使わず、自己流になってしまうことです。
これらのことばの前後にあるものが、筆者の意見の可能性が高いのです。
読むときにこれらを意識し、筆者の意見をとらえること。
それだけで本当に国語の問題は解けます。