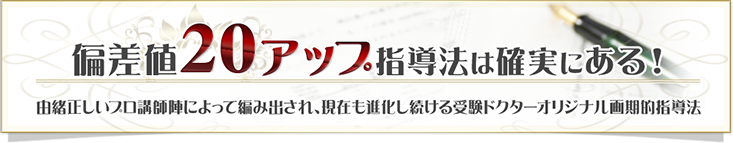こんにちは。理屈家講師の永田です。
2025年度の入試が終わったと思ったらもう、2026年度入試に向けた模試が各塾で始まる時期となってきました。2回前の記事で、本番の試験で答案の見直しをするときの心構えを書いたのですが、そもそも答案の見直しにはどのようなことが必要なのかを書いていませんでした。今回は、テストを受けながら答案を見直すときに注意しなくてはいけないことについて書きたいと思います。
まず前提として、試験時間がぎりぎりだとか足りない場合はこの記事の内容を気にすることはありません。まずは解くスピードを上げたり、捨てる問題を見極めたりを考えましょう。
さて、一通り問題を解き終って少し時間が余っているとしましょう。ここで答案の見直しをするときに必要なことは何でしょうか。試験が終わってからの見直しと一番違う点は、「まだ解答がわからない」ということです。はっきりと✕がついた問題であれば、自分がどこかで間違えたのは明らかなのでその場所を探しにいくことはできるでしょう。しかし、解答がわからない状態では、そもそも自分の答が正しいのか間違いなのかもわからず、依って立つ確かなものが見当たらない状態なのです。
では、その状態で答案を見直すために必要なものは何か。答えはタイトルに書いた「批判的思考(クリティカルシンキング)」です。「批判的思考」を辞書で引くと、「物事や情報を無批判に受け入れるのではなく、多様な角度から検討し、論理的・客観的に理解すること」(デジタル大辞泉より)とあります。この言葉は使う人によって多少意味は異なるのですが、「『マイサイド・バイアス(自分の信念が正しいと思ってしまうこと)』に陥らずに自他の思考を吟味する」と表現している人もいます。今回のテーマ、模試の時間の中での解答の見直しということで言えば、「自分の解き方は正しかったのか、一度疑ってみる」ですね。
実際に答案の見直しをするにあたって、どのようなことが必要になるか考えてみましょう。一通り問題を解き終って見直しの時間に入ります。このとき、「さっきこの問題を解いていた自分は、どのように解いていたのだろうか」ということを確認する必要があります。ところが、ついさっき解いていた問題ならいざ知らず、試験の始めのほうに解いていた問題なんて少し記憶から飛んでいるものです。ということでまず大切なこと。特に算数では、
・自分がどのように考えたのか、あとから見直して分かるように記録を残しておきましょう。
さて、数十分前の自分が何を考えていたのかは分かりました。では、その考え方が正しかったのかを確認していきましょう。ただ、「自分を疑う」というのはバランスが難しく、自信を持ちすぎて自分を疑えないと自分のミスを探すことはできませんし、かといって自信がなさすぎると疑心暗鬼に陥って正しいものまで疑ってしまいます。なかなか難しいですが、見直しのときは、「自分の答案を客観的に見る」、つまり、他の人が書いた答えをチェックしているような感覚になれるのがベストだと思います。舞台に立つ人が「演じている自分を外から見ている自分がいる」というようなことを言うのを聞いたことがありますが、似た感覚だと思います。他に「私は自分を客観視できるんです」と言った総理大臣がいたのですが、これは20年近く前の話ですね。脱線もありましたが大切なこと2つめ、
・自分の答案を客観視できるように慣れていこう。
ここまでくればあとは、解き方のステップそれぞれを根本原理や基本法則、計算に分解して確認していくだけです。例えば速さの問題であれば、時間が同じなら速さと距離は比例、距離が同じなら速さと時間は反比例。場合の数であれば、区別できるものの並べ方はかけ算で出せる。力学の問題であれば力のつり合い。化学反応の計算であれば定比例の法則や質量保存の法則。日頃の勉強の中で、「いつでも成り立つ基本的な原理」を自分の中で確立して、さらにバリエーションを増やしていくことが求められます。大切なこと3つめ、
・疑う必要のない原理原則を確立しよう。
以上が試験時間内での答案見直しに必要なものになります。人間誰しもミスはあるもの、毎回完全な答案を作るのはまず無理です。本番で自己ベストの答案を作れるように、模試をしっかり練習として活用していきましょう。
最後に、自分が昔言われて今でも気に入っている言葉を書いて終わりにしたいと思います。
「練習は本番のつもりで、本番は練習のつもりで。」