皆さんこんにちは。
受験Dr.の理科大好き講師、澤田重治です。
中学受験を志す皆さんは、
おそらく「紫キャベツ液」というものを知っていると思います。
水溶液が酸性か中性かアルカリ性かを調べる指示薬として、
理科の入試問題にもよく登場しますね。
強酸性…赤色
弱酸性…ピンク色
中性…紫色
弱アルカリ性…緑色
強アルカリ性…黄色
となっていることが多いようです。
(※中性の色を青色としたり、ごく弱いアルカリ性に青色を入れたりすることもあります。)

では、質問です。
「紫タマネギ液」の色の変化は知っていますか?
「ブルーベリー液」の色の変化は? 「赤シソ液」は?
そんなの聞いたことないっていう人が多いですよね。
私も、入試問題で「赤シソ液」を見たことはありません。
でも、答えは意外と簡単で、すべて紫キャベツ液と同じになります。
紫キャベツの色の正体「アントシアニン」
紫キャベツ液の色の原因となる色素は「アントシアニン」といいます。
一時期、目に良いと言われて有名になりましたので、
大人の方は聞き覚えがあるかもしれません。
実際、目のレンズ(水晶体)の厚さを変えることでピントを調整している
「毛様体」という筋肉の血流を一時的に増やす効果はあるようですから、
目に良いことは確かでしょう。
ただし、視力を回復するほどの力があるわけではないようですね。
このアントシアニンは、植物のからだを紫外線から守るはたらきがあるようで、
意外と多くの植物に含まれています。
とりわけ、先ほど挙げたような紫色の食品は、ほとんどがアントシアニンを含んでいます。

だから、同じ色の変化をしたのですね。
アサガオの花がSOS ?!
以前、交通量の多い幹線道路わきの駐車場で、
金網にツルを巻きつけて咲いている野生のアサガオを見つけたことがあります。
濃い青紫色の花を咲かせていたのですが……
明け方に降った雨粒がついているところだけがピンク色に変色し、
まだら模様になっていたのです。
濃い紫色の地にピンクの斑点……ちょっと毒々しい配色ですよね。
実は、アサガオの花びらに含まれている色素もアントシアニンの一種なので、
ピンク色は水滴が酸性になっていたことを示しています。
酸性雨が原因なら、花びら全体の色が変わっているはずですから、
おそらく車の排気ガスが雨粒に溶け込んで酸性になり、
水滴の部分だけ花びらをピンク色に変色させてしまったのでしょう。
ひっそりと咲いた花が大気汚染のSOSを出しているような気がして、
何だか心苦しい気持ちになったものです。

自然界の色素は「指示薬」になるものが多い
ところで、アサガオの花びらの色だけが特別なのでしょうか?
もちろんそんなことはありません。
「指示薬」となるものが多く存在します。
考えてみれば、リトマス紙に使われている色素も、
「リトマスゴケ」という苔から抽出した色素ですからね。
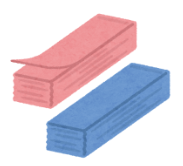
中でも、カラフルで楽しいのは花びらではないでしょうか。
花びらを染めている色素にはいろいろな種類があり、
そのほとんどが指示薬としてのはたらきを持っています。
様々な種類の花を集めて花びらを煮出し、
いろいろな「指示薬」を手作りして色の違いを比べたら面白い実験になりますよ。
来年の夏休みの自由研究にいかがでしょうか?
次回もまた、楽しくて中学受験のためになる「身近な科学の話」をお届けします。
どうぞお楽しみに!




